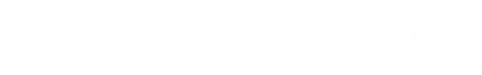2024.10.03
根羽の森をふたたび村の「宝」に。未来につながる森林づくりへのチャレンジ

「村の人たちに話を聞いていくと、いろんな思いが山の中に見えてくる。みんなの思いが活きる森林づくりをすることが理想です。」
長野県の最南端に位置する根羽村。人口約900人の村で、森林が占める面積は92%。林業を村の主産業として、世代を超えて森を守り、森と共に暮らしてきました。
そんな根羽村が「輝く農山村地域創造プロジェクト」を通して取り組むのは、未来につながる森林づくり。これまでにない森林の付加価値を生み出す新たな森林経営により、森の価値を高め、村民が森をもう一度「宝」とみなすことを目指します。 根羽村の魅力や抱えている課題、プロジェクトにかける思いを、村役場職員の鈴木秀和(すずきひでかず)さん、松下直樹(まつしたなおき)さん、この事業のために長野県庁から根羽村に派遣されている戸谷亮太(とやりょうた)さん、根羽村森林組合の大久保裕貴(おおくぼゆうき)さん、そして、役場と連携しながら村づくりを推進する一般社団法人 ねばのもりの杉山泰彦(すぎやまやすひこ)さんにお話を聞きました。
先人の思いによって守られてきた根羽の森

長野県の南西部最南端に位置する根羽村は、村の総面積89.95㎢の92%を森林が占めています。根羽村では、村長が森林組合長を兼ねており、村民の全員が山持ちであり森林組合の組合員という、全国でも珍しいシステム作りを行っています。
鈴木さん 「根羽村は、代々山づくりで材を成してきた地域です。かつて、村が各家庭に山を貸し与えたことで、村の誰もが木を育てて財産にする仕組みがありました。『山の木を切って子や孫の学費にする』といったように、山が財産になっていたんです。」

しかし、海外から安い木材が輸入されるようになるなど、時代の流れによって山の価値は下がってしまいました。林業の衰退に伴い、かつて村内に7軒あった製材所は次々と閉鎖。このままではいけないと、平成七年に最後に残った製材所を森林組合が引き継いだことから、根羽村の再挑戦が始まりました。

大久保さん 「根羽村の森林組合は、伐採から板材への加工、さらに商品づくりまでできる一貫した設備を持っています。木を植え・育て・伐採する第一次産業、そして丸太を加工する第二次産業、さらに加工した製品を販売する第三次産業が、村内で全て完結する『トータル林業』の仕組みを整えてきました。」

流域全体で連携をし、水源を守りながら森の活動の事業化を目指す

さらに、根羽村独自の森づくりのあり方の一つが、下流域との連携です。
鈴木さん 「『水を使うものは自ら水を作れ』という言葉があります。大正時代から、下流域の安城市と森を通じたつながりがあったり、愛知や岐阜の学校の子どもたちや、企業が環境学習のために根羽村を訪れたりと、流域全体で連携する流れが培われてきました。」

これまで、そういった活動の受け入れはボランティア的に行われていました。しかし、環境保全の関心が高まる現代において、鈴木さんたちは森での活動を事業化できる可能性を感じています。

鈴木さん 「従来通り、ただ植林を行うだけではもったいない。森を守る活動にも価値がありますし、森を通じて村の外の人と継続した関係を築いていきたいですね。根羽の山や木を使って、環境学習やアクティビティの機会を提供することで、流域内に関係人口を増やし、共に水源を守りながら、持続可能な事業の形をつくりたい」
なんのために、どこを目指すのか。森づくりの次のビジョンが必要

そんな根羽村が、「輝く農山村地域創造プロジェクト」で目指すのは、未来につながる森林づくり。これまでにない森林の付加価値を生み出す新たな森林経営により森の価値を高め、村民が森をもう一度「宝」とみなせるようになることを目指します。
松下さん 「かつて木を植えた人たちは、山に愛着と関心があり、『良い木を育てて次の世代の財産に』という思いを持って山づくりをしてきました。しかし、世代が代わり、木の価値が下がり、山への関心が薄れてきている。ただ木を切って使うだけでなく、山の価値自体を高めていかないといけません。」


村の内部、そして外の人たちをつなぐコーディネーターの役割をしているのが杉山さんです。プロジェクトの立ち上げ当初は、「新しい製材機を購入しようか」という声もあった中で、ハード面の強化よりもソフト面からのアプローチが必要だと提案しました。
杉山さん 「普段から森林組合や村役場の面々とコミュニケーションを取る中で、『森づくりの次のビジョンが必要だ』と感じていました。根羽村には、山があり、木があり、製材所もある。すでに武器はたくさんあるんです。でも、それを使える人がいないし、使う機会も十分にない。そもそもなんのために、どこを目指すのか、みんなが一つになれるコンセプトを定めたいです。」

まずは村民が根羽の森についてどう感じてるのか話を聞いた上で、村の現状と未来に対しての共通認識をまとめ、コンセプトづくりのための調査や勉強会、ワークショップを行う計画です。伊那谷で森づくりを行う「やまとわ」や、信州大学農学部など、村の外の人たちとも協働しながら、どんなアプローチができるのか探っていきます。
戸谷さん 「根羽の持つ価値をまずは根羽の人たちが認められるようになることも、これからの森づくりにおいて大切なんじゃないかと。たとえば、猟友会の方々が山に入って猟をすることも、都市部の人向けのツアーになりますし、村のおばあちゃんがただいつも通り山に入って散歩することも、外の人からしたら新しい発見につながるかもしれない。根羽の人たちの、『当たり前』が価値となり、地域にお金を生み出す仕組みは、このプロジェクトで目指す形の一つですね」
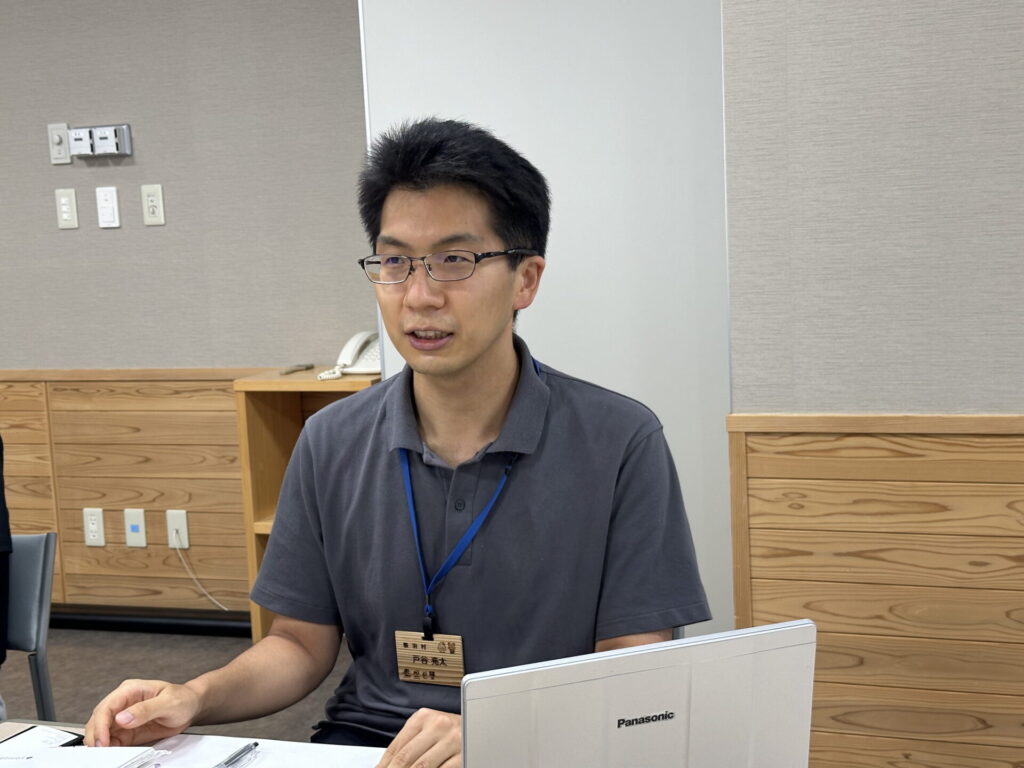
森を適切に管理し、未来へつなげる

ヒアリングやコンセプト作りを踏まえて、根羽村が取り組もうとしているのが森林のゾーニングです。これまで山が地域でどのように活用されてきたのか、また環境面の特徴や状況などあらゆる情報を整理し、重視すべき森林の機能を絞り、生産林、環境林、里山林にゾーニングを進めます。
戸谷さん 「村の人たちに話を聞いていくと、『小さい頃、枝打ち作業についていって山の中を駆け回って遊んだ』『子供が成長して、大人になったときに木を切った収入で送り出してあげられるように木を育ててきた』など、いろんな思いが山の中にはある。そういったエピソード一つ一つが見える森林づくりをすることが理想です。」
「林業だけで考えると、問題が山積みでいろいろな壁がある」と大久保さん。しかし、地域の強みを生かす「輝く農山村地域創造プロジェクト」であれば、多方面と連携し、根羽村ならではの動きが生まれるのではないかと期待を膨らませます。
大久保さん 「林業をかっこいい仕事にしたいですね。根羽村に帰ってきて感じたのは、個性的で面白い人たちが多いということです。根羽の森に関わる人たちは、生き様がかっこいいんです。これだけ山があって、面白い人たちが集まってきているんだから、それを活用できずに、山が荒れてしまうのはもったいない。」

プロジェクトの期間は3年間。一方、林業は、『親で植えて、子で育て、孫で伐る』と言われるほど長いスパンが必要な産業です。たとえば、赤松の木は一列の枝が出るのに一年かかるそう。その時間軸の中で、自走できる新しいビジネスモデルを確立していかなければなりません。
杉山さん 「派手なことをやらなくていいから、ちゃんと持続する事業を作りたいですね。今、根羽村では空き家に住みたい人と空き家をつなげるマッチング事業が進んでいます。林業でも、山を持っている人と、山を使って何かをしたい人がつながる仕組みも作りたい。そうして山を使った人が、今度は山を作る側になり、循環が生まれていくことが理想です。」
根羽の森の価値を新たに生み出し、未来へ循環させていく。根羽村の今後の取り組みの様子は、現地ライターによるレポートでお届けしていきます。
取材・執筆:風音