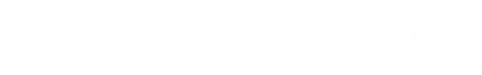2025.10.30
山や森林のいまをどう伝え、どう取り組むか【東京チェンソーズ視察レポート】
上流と下流の間を行ったり来たりしながら、どっちもいい状態を考える。
nebaneの考える循環を目指すため、山や森林のいまをどう伝えて循環を生み出していくか。
多摩川に合流する秋川流域に位置し、村の面積の93%が森林の東京都檜原村で「森と街が共生する社会」の実現を目指す東京チェンソーズへ10月2日に伺い、代表取締役の青木さんと木材コーディネーターの戸田さんに今の取組をお聞きしました。
「東京で森林を考える」時、森や木とのつながり方には無限の可能性があることを実感しました。

森をつくる現場で森を開く(MOKKI NO MORI)
最初に、利用することが森にとってプラスに働くよう東京チェンソーズが整備している山林フィールドへ伺いました。
幅2.5mの道を作り、木材搬出が出来る体制を整え、葉が重なり合って満員電車のようだった木が間伐を行ったことにより風で揺れている様子、日光が当たるようになり地表の植物が成長し雨水が緩やかに地中へ染み込む環境が生まれていること、広葉樹林でも整備されず荒れている場所もあることなどフィールドを歩いて森林の様子を見ながら教えていただくことで、森の有用性や利用の意味を理解した時、面白いと思ったことは人に伝えたくなります。

更に、適切な森林管理と加工・流通過程の管理が行われていることを確認して保証する国際的な森林認証を取得することで、森づくりに第3者の視点が加わっています。
日本では認証を受けた木材が十分な価格で取引されないという課題はありますが、第3者による指標と資料があることで説得力が増します。
フィールドに来た人が聞いた説明を職場や地域に戻った時、同じ熱量で分かりやすく伝えられる材料としていました。

フィールドの中で、真っすぐ育つことに由来する「スギ」という名前や縄文時代から雨の多い日本で良く使われてきたスギの見方が変わります。
山で働く人が減っている中、人が植えたスギやヒノキなどの木材の使い方をどうするかを考えるキッカケとして、面白いから入れることが素敵だと思いました。
この森ではアウトドアフィールドとして場を開いたり、1年に1回山開きを行ったりすることで、山に行きたいけどどう行けばいいか分からないという方でも森に入りやすくしています。
同時に、このフィールドで行われる作業によって森がより美しくなるよう、森林価値の最大化、山や木の個性を引き出していました。
1本まるごと利用
東京チェンソーズが進める「1本まるごと利用」は非常にユニークです。
国際的な森林認証の取得に伴い、1年間の成長量に応じた量の木まで搬出できるという制約条件が生まれました。
そこで、木材は幹部分のみが利用されがちなところを、「1本の価値をどこまで最大化するか」という発想のから「枝や根も含めて木1本全てを資源として使い切る」方法を考えていました。
蒸留
通常捨てられてしまっている枝葉を集めてアロマを抽出しています。
木材として木を使う空間で香りをともにお届け出来るよう、工夫を凝らしていました。

木材置き場
檜原村木材産業協同組合の木材置き場では平らな空き地がない檜原村の標高500mの山の上で風通しのよい土地に天然乾燥材が置かれていました。
製材した木や丸太に加えて根っこまで置かれている場は壮観でした。

檜原村の目的地(森のおもちゃ美術館)
「檜原村を日本一有名な木のおもちゃ村にしたい」という想いで始まった檜原村トイビレッジ構想で2021年にオープンしたミュージアムは、ドライブや登山客が多かった檜原村に若い子育て世代を呼び込む場となっています。
檜原村には年間25万人の観光客が来ているそうで、そのうちの5万人が観光資源のなかったエリアにあるおもちゃ美術館に来ているそうです。
檜原村の特産品であるゆずやじゃがいもを模したおもちゃや山ひろばなど、大人でも手に取って触れて遊びたくなる空間に檜原村の木がふんだんに使われていました。

おもちゃ工房
杣ものなどのプロダクトや特注品づくりの相談が出来る工房では、1つ1つ違う山からの素材を見つめてつくる現場も見学させていただきました。
製品を見て使うことの出来る場所と実際の製品がつくられる場が隣にあって接続されている、構想が実を結んでいる姿はとても勉強になります。

地道な積み重ねと新しい価値の創出
1本まるごと利用も当初はこんなものが使えるのかと思われていたところから少しずつ口コミで伝わり浸透してきたものが伸びてきたところと言います。
身の丈に合わせてコツコツと重ねてきた実際の動きがあるからこそ、発信する全ての内容に実が伴っている姿がとても分かりやすく伝わり、東京チェンソーズのカッコよさをひたすらに体感する視察となりました。

川上と川下を顔の見える関係として川中を薄くするため山の人、町の人双方に伝えられるようカメラを常に持ち歩く戸田さん
見据える将来の姿に向けて何を制約条件として、どう取り組んでいくか。
nebaneも多くの取組の中で考えるとともに、継続していきたいと思います。