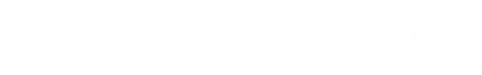2025.07.18
川上-川中-川下をめぐる木材流通と広がりを広葉樹のまちで学ぶ【飛騨の森の視察プログラムレポート】
村の面積の7割を占める杉・ヒノキの山を今後どう利活用すべきなのか。根羽村で取り組んでいる「輝く農山村事業」では、全国のかつて林業で栄えた村が共通課題として持っている人工林の利活用についてどう向き合うべきか、がひとつの重要なテーマとなっています。
森林の7割を広葉樹が占める岐阜県飛騨市を訪ね、株式会社飛騨の森でクマは踊る(通称:ヒダクマ)の皆様に広葉樹の新たな価値創造とまちづくり、広葉樹の可能性に挑戦する林業(川上)・製材(川中)・製造(川下)の取り組みを7月10・11日に飛騨の皆様に伺ってきました。
様々な主体とのコラボレーションにより価値を生み出していく裾野の広がりを感じました。

森と地域、デジタルものづくりへの扉を開くカフェ・滞在制作できる場(FabCafe Hida)

ヒダクマの井上さんのご案内で、モノを見に来る、作る人とのコミュニケーションの意志疎通ツールとして使われている、ストランドボード(内装材)や森の色を集めたクレヨンなど、様々なモックアップやサンプルを見ました。
森からいつでも必要な樹種が切り出せるわけではなく、乾燥工程を踏まえると常に欲しい在庫があるわけではないこと等、森側の事情を踏まえて森を起点としたデザインをどうすれば作れるかを対話しながら制作できる場となっていました。
豊富な資源量を活かした広葉樹のまちづくり(飛騨市役所)

豊富な資源量と広葉樹を活用するために必要なリソース(素材生産者・広葉樹製材所・高い技術を有する使い手など)を有する飛騨市の特性を活かした広葉樹のまちづくりの挑戦について教えていただきました。
趣旨に賛同する飛騨地域の関係プレイヤーと行政により飛騨市広葉樹活用推進コンソーシアムを設立し、多様な広葉樹と多様なニーズを丁寧につなぐ新たな広葉樹流通の仕組みをつくり、持続可能な広葉樹林業を目指すための基本的な方向性や技術的なガイドラインを策定するなど多様な取り組みを行っていました。

また、市役所の応接室には、飛騨市の多種多様な木材を利用した天板プレートやグラデーション上に並べた壁のホオノキ材、木目が透けるようブナを突板加工したランプシェードなど、飛騨市の広葉樹を活用した空間の魅力を最大限にPRできる場となっていました。
この応接室はヒダクマと矢野建築設計事務所とで設計し、飛騨市の優れた木工技術を持つ事業者と協力し作り上げたものだそうです。天板プレートは広葉樹の樹種に応じた色や木目の違いを一目で感じることが出来ました。
広葉樹の原木を大切に製材する(西野製材所)

広葉樹材は一つ一つの木の節や反りなどにより形状が違うこと、針葉樹より含水率が高く、固くて重い特性に合わせた製材を行っていることを教えていただきました。
材の固さに対応するため製材機の回転数を落とし、樹種に応じて刃も変えていること、通常は1年程度天然乾燥を行った後、乾燥の度合いに応じて人工乾燥に入る等、広葉樹の特性に合わせて丁寧に製材がされていました。
飛騨の広葉樹を集め仕分け流通する(柳木材)

広葉樹は直材、小曲材、節材を大きく2つの価格帯に分けて販売しているが、約20万種の膨大な樹種を有する広葉樹は樹種によっては一度に数本しか中間土場に出てこないこともあり、モノによっては価格をまとめて仕分けすることもあるそうです。
中間土場に山で処理していた木を持ってこられるようにするには、丸太が一定の料金以上で買われる必要があります。様々な方に買っていただくことで経済性を証明していこうと、小径材がより手間のかかるものであっても、山主や施業者に還元できる価格で売れる方法を考えていました。
地域の広葉樹流通拠点の入口(森の端オフィス)

建築分野における広葉樹の可能性を具現化するオフィスとして、乾燥工程を実験的に短期間で出来るよう1年程度かかる天然乾燥の工程を省いて人工乾燥を行って建材としたオフィスで、切り出した森と使われる木材の樹種の割合が同じという、森をそのままスケールした空間となっていました。
お話しをお聞きした皆さんを始めとして、多くの方がつながり関わることで建てられた空間が森とまちの境界上にあることで、飛騨の地域の想いを伝えてくれる素敵な場でした。
川上~川下の自然な流れの中で素材屋として回る(やまかわ製材舎・及川さんレクチャー)

山の仕事をするために製材工場で働いた後、これから広葉樹の木材流通を作ろうとしていた飛騨市で地域おこし協力隊となった及川さん。
当初は広葉樹のまちづくりに向けて、それぞれのプレイヤーが持つ余剰のキャパシティの中で対応していたそうですが、広葉樹の需要を拡大していく過程で製材所がボトルネックとなっていたため、マーケットのチャンスをつかめる受け皿として遊休状態となっていた工場を再生し、現在はやまかわ製材舎として経営しています。

飛騨市の広葉樹は当初9割以上がチップ化されていたところ、2020年から地域の小径木を集める中間土場へ人を呼ぶことで、マーケットに出会い本当の価値を見つけ、あるいは必要とされる面を聞き取り、在庫のない状態から新たなものを作ることで木材としての販路を広げていました。
飛騨市は広葉樹の木材流通が川上から川下まで地域内で完結しますが、川下の裾野が地域外にも開かれるよう流通の幅を広げるとともに、市場・売り手が必要とする量を供給できるラインを通すために広葉樹活用コンシェルジュとして全体の流れ・バランスを整える役割を担っていました。
そこから広葉樹のまちづくりのフェーズが更にシフトし、川中の素材屋として持続性のある流通に向けて、コーディネーターなしでも勝手に流れる産業を理想に川上や川下を両面知っている製材所として取り組む意義を教えていただきました。
広葉樹施業をやる意味(飛騨市森林組合)

広葉樹は針葉樹に比べて伐採も造材も運搬も難しく、面積当たりの材積も少ないため、飛騨市の補助金があってなお広葉樹施業の方が収入にならないという実態から広葉樹の天然更新実態まで、木材流通における川上の状況について詳しく教えていただきました。
森林組合として収入源となる針葉樹施業に限らず広葉樹施業をしているのは、飛騨市広葉樹のまちづくりに向けた取組、柳木材の先代社長への感謝の思い、飛騨市の森林の7割が広葉樹林という実情を考えてのことだそうで、飛騨市森林組合で地域の山を買い上げるなど、山を守る主体としての姿を伺いました。
広葉樹発信拠点にもなる産直市場そやな

一緒に山を登っていろんな景色を見る(ヒダクマ松本さんからのレクチャーとディスカッション)

顧客と飛騨市とを全体性の中から繋いでいるヒダクマで具体的なビジネスとしてマネタイズをどうしているのか、飛騨市の出資も受けている立ち位置についてなど、数々の取組が注目されているヒダクマのリアルを時間一杯伺いました。
ヒダクマが広葉樹のまちづくり全体を回し続けるのではなく、多くの主体が現れ有機的に動くことで、1プレイヤーとしてプロセス含めて飛騨に共感し、価値を感じてもらえるような様々な取組、より新しいことへの挑戦を行っていました。
飛騨には、何か気になるぞ、一緒に手を組んだら面白そうだな、というフックがたくさんあるように見る側からは感じる、とても学びの多い視察となりました。
いただいた学びをnebaneの取組に活かせるよう、上流と下流を行ったり来たりしながら、川上から川下までスタートラインから一緒に考えていきたいと思います。